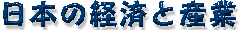
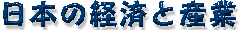 |
*** 213 ***
... - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - ... - Back
|
太陽系外からやってきて飛び去っていく 星間飛行する天体を初めて発見か? 国際天文学連合 (IAU) の小惑星センター (Minor Planet Center) は 10 月 25 日、太陽系の外から飛んできたと考えられる小さな天体「A/2017 U1(旧名 C/2017 U1)」を発見したと明らかにした。 恒星間を小惑星や彗星が飛行することや、それが太陽系にも飛来することは、理論上予想されていたが、実際に発見されたのは初めてとなる。 帰ってくる彗星、帰ってこない彗星 たびたび夜空に現れては、長い尾をひく姿で世間の話題をさらっていく彗星。 別名ほうき星とも呼ばれるこの天体は、これまで 3,000 個以上もの数が見つかっているが、そのどれもが太陽系の中の、海王星より外側の「エッジワース・カイパーベルト」や、さらにその外側にある「オールトの雲」と呼ばれる領域で生まれたと考えられている。 こうした彗星は、その軌道から大きく「周期彗星」と「非周期彗星」に分けられる。 周期彗星というのは、太陽のまわりを一定の周期で回っている彗星のことで、たとえば有名な「ハレー彗星」は約 76 年の周期で太陽のまわりを回っており、私たちの前に姿を現す。 一方、非周期彗星というのは、太陽を回る周回軌道ではなく放物線の軌道を飛んでおり、一度太陽や地球に近づくと二度と帰ってこないと考えられている、文字どおり周期性がない彗星のことである。 たとえば 2013 年に大彗星になるといわれていたものの、太陽に接近した際に蒸発して肩透かしに終わってしまった「アイソン彗星」などがこれにあたる。(筆者注 : ただし、周期彗星も途中で軌道が変われば周期性がなくなることもあるし、非周期彗星も数百年、数万年といった遠い将来に帰ってくる可能性がないわけでもない。) いずれにしても、これまでに発見された周期彗星はもちろん、非周期彗星もすべて、生まれたのは太陽系内であると考えられている。 しかし 2017 年 10 月 19 日、ハワイのハレアカラ天文台にある、複数の望遠鏡で夜空を見渡し未知の小惑星や彗星などを発見することを目的としたシステム「パンスターズ」が、少し変わった彗星を発見した。 命名規則に従い、この彗星には「C/2017 U1」という名前が与えられた。 ハワイ大学天文研究所 (IfA) の研究員である Rob Weryk 氏は、すぐに C/2017 U1 が奇妙な天体であることに気づいたという。 「この天体の動きは、太陽系の小惑星や彗星の軌道では説明がつかないものでした。(Weryk 氏)」 Weryk 氏はすぐに、IfA の卒業生である Marco Micheli 氏に連絡をとり、カナリア諸島テネリフェ島にある欧州宇宙機関 (ESA) の望遠鏡を使ってこの天体を撮影し、分析を行った。 そして最終的に「C/2017 U1 は太陽系の外から来たものだ」と結論づけた。 ある彗星が周期彗星なのか、非周期彗星なのかは、軌道の「離心率」というものを調べることでわかる。離心率というのは、その軌道の形がどれだけ円形から離れているかを表す値で、真円でも楕円でも、とにかく一周がつながった軌道なら離心率は 0 以上 1 未満、もし放物線を描く軌道なら離心率はちょうど 1 となる(実際の彗星では、ちょうど 1 になることはない)。 しかし C/2017 U1 の軌道は、この離心率が 1 を超え、約 1.19 にもなっていた。 これほど離心率の大きな軌道のことを「双曲線軌道」といい、この軌道の彗星は中心となる天体、すなわち太陽に二度と戻ってこない非周期彗星であるばかりか、太陽から離れたあとにさらに遠くへ飛んで太陽系の外に出ていってしまう。 そしてそれは言い換えれば、この彗星は別の惑星系で生まれ、星間空間を飛行し、はるばる太陽系へやってきたということにもなる。 離心率が 1 を超える、双曲線軌道の彗星が見つかったのは C/2017 U1 が初めてではない。 たとえば 1980 年に発見された「ボーエル彗星」は、1.05 という離心率をもっている。 しかし、ボーエル彗星はもともと約 710 万年もの周期をもつ彗星だったものの、木星に近づいた際に軌道が変わり(摂動という)、離心率が変化したと考えられている。 そのため、これから太陽系の外に出ていくことはあっても、生まれたのは太陽系の中だったと考えられる。 一方、C/2017 U1 の 1.19 という値は、ボーエル彗星に比べはるかに大きい。 1.05 と 1.19 という数字だけを比べると、ほんのわずかな違いに見えるものの、離心率においてはまったく意味が変わってしまうほどの違いがある。 もともと太陽系内にあった天体、すなわち離心率 1 以下の天体の軌道を、離心率 1.19 の軌道に変えるためには、木星などの影響ではとてもエネルギーが足らない。 その点からも、太陽系の外からやってきたと見るのが自然だと考えられている。 米国航空宇宙局 (NASA) のジェット推進研究所 (JPL) の地球近傍天体研究センター (CNEOS) の科学者、Davide Farnocchia 氏は、「C/2017 U1 はこれまで見てきた中で最も極端な軌道をもっています」と語る。 「これほどまでに速く、かつこのような軌道をもった天体は、太陽系から出て、そして二度と戻ってくることはないと自信を持って言うことができます。」 IAU 小惑星センターの Gareth V. Williams 氏は「この天体のさらなる観測が非常に望まれます。 これまでの観測結果に間違いがないと仮定したとして、この天体は大きな双曲線軌道を持っていると考えるのが唯一の答えです。 さらなる観測でそれが裏付けられたら、星間彗星の最初の例になるでしょう。 とてもエキサイティングです。」と語っている。 なお、10 月 25 日には、ハワイ大学による観測から、この天体は彗星のようにガスを出すような活動はしておらず、むしろ小惑星に近い天体であることがわかった。 そのため、当初つけられた C/2017 U1 ではなく、小惑星を意味する「A/2017 U1」という名前に変更されている。 彗星はもちろん、小惑星だったとしても、太陽系の外からやってきたと考えられる天体が見つかったのは今回が初めてである。 CNEOS の責任者を務める Paul Chodas 氏は「私たちは何十年もの間、この日を待っていました。 小惑星や彗星が星と星の間を移動し、ときには私たちの太陽系を通過することは、以前から理論的に考えられてはいました。 そして今回、それを初めて見つけることができたのです。 これまでの研究では、この天体が『星間天体』である可能性が高いことを示していますが、さらなるデータがそれを確認することに役立つでしょう。」と語る。 現在までの観測によると、この A/2017 U1 はこと座のヴェガがある方角、太陽系の黄道のほぼ真上から、秒速約 25.5km でやってきたと考えられている。 ただし方角が一致しているだけで、ヴェガからやってきたという証拠はない。 そして 9 月 9 日に太陽に最接近し、軌道を大きく曲げて、10 月 14 日には地球から 2,400 万kmのところを通過。 そして太陽系の黄道の上面側に戻り、現在は太陽に対して秒速 44km という速さで飛んでいるという。 これからもどんどん遠ざかり、いずれは太陽系を脱出することになる。 天体の大きさは、あくまで推測値として直径約 400 - 160m ほどであると見積もられている。 すでに明るさは 21 等級にまで暗くなっているため、望遠鏡で観測できるチャンスは残り少ない。 今も続く観測と、これまでの観測データから、どこまでこの天体の正体に迫れるか期待したい。 (鳥嶋真也) - MyNavi 2017 年 10 月 27 日 - ◇ ◇ ◇ 太陽系来訪の星は葉巻形 観測史上初の恒星間天体 【ワシント】 観測史上初めて太陽系外から飛んできた「恒星間天体」と認定された小惑星が、細長い葉巻のような形をしていることが分かったと米航空宇宙局 (NASA) が 20 日、発表した。 「太陽系以外の恒星やその周りの惑星がどのように形成されたかを解く鍵になる」としている。 小惑星は米ハワイ大などのチームが先月発見し、ハワイ語で偵察者を意味する「オウムアムア」と名付けられた。 その後の解析で、長さは 400 メートルほどで、幅の約 10 倍もあることが判明。 太陽系でこれまで見つかった天体だと、長さはせいぜい幅の 3 倍程度だという。 7 時間ほどの周期で自転しながら、秒速38キロで飛行。 岩と金属でできていて、水や氷はない。 何億年も宇宙空間を旅して宇宙線を浴びたため、表面は赤みを帯びていると推定される。 いずれは太陽系を離れて飛び去る。 現在は火星の軌道よりも外側の宇宙空間を飛んでおり、2019 年 1 月には、さらに外側の土星の軌道を越えるという。 - 共同通信 2017 年 11 月 21 日 - 巨大隕石衝突、数百キロずれたら今も恐竜繁栄? 6,600 万年前に恐竜を絶滅に追い込んだとされる巨大隕石いんせきの衝突が数百キロ・メートルずれていたら、いまも恐竜は繁栄していたかもしれない - -。 そんな研究成果を東北大と気象庁気象研究所のチームがまとめ、英科学誌「サイエンティフィック・リポーツ」に掲載された。 メキシコ・ユカタン半島には、直径約 10 キロ・メートルもの巨大隕石が衝突した痕跡があり、衝突に伴う環境変化で恐竜が絶滅したとされる。 海保邦夫・東北大教授(生命環境史)らは、隕石衝突で地面が燃えてすすが舞い上がり、太陽光を遮って気温が下がったとする学説をもとに、具体的な条件を検討した。 チームによると、当時の地球上の気温は約 16 - 28 度で、月平均 8 - 11 度も気温が下がると、食物連鎖が崩れるなどして恐竜が死に絶えたという。 - 読売新聞 2017 年 11 月 10 日 - |
... - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - ... - Back